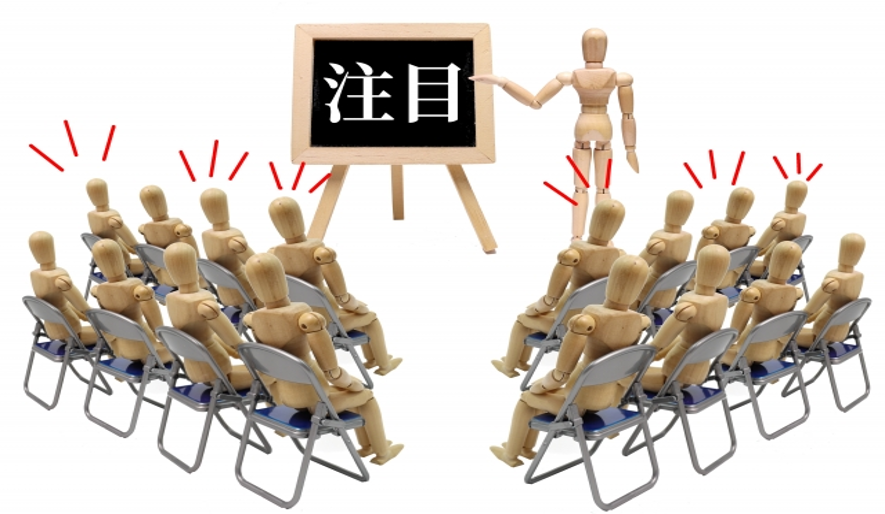コミュニケーション

興味を引く情報はチームワークで

卒業生・保護者の方々に振り向いて貰うには
「興味を引く情報」を発信するといっても。。。 一部署の力だけでは、なかなか「ファンづくり」に至る情報発信は難しいんです。そう必要なのはチームワーク!某大学の実話
過去に某有名私立大学の事務局長を務めた方が昔話としてお話しくださいました。 「自分が募金担当となったとき、まず卒業生に寄付金の要請をお手紙で送ったところ、苦情のお手紙をたくさん貰ってしまった。苦情の多くは、『これまで大学が何をしているのかロクに情報も寄こさないのに、やっと来たと思ったら中身は寄付の依頼だけ?』と言う内容だった。確かに何もしてこなかったのは事実。 そこでTOPに決断しもらい、大きな予算を投資して学報を年2回送り続けた。すると3年目あたりからようやく励ましや応援の手紙が来るようになった。当たり前と言えば当たり前だが、卒業生は財産と言いながら、いかに信頼関係構築に手を抜いていたかということになる。学報はもちろん今でも続けていますよ」という内容でした。
耳の痛いアンケート結果
弊社実施の卒業生アンケートによると、学報到着者の内、実際に読んでいる人はわずか15%。若年層ほど低い傾向でした。読んだ人からも「面白くない」「役に立たない」と言う声が多くありました。 また、当時の学長についても、「入学式や卒業式の時には見たが名前は憶えていない」「知らない」という回答が多数。同様に同窓会長も身近な存在ではないようでした。興味を引く情報とは?
多くの大学の学報やメールマガジンを拝見すると、冒頭に偉い方のお話から始まっているものが大半ですが、興味を引く内容には大事なポイントがあります。 全ての人が興味を持つ情報があればよいのですが、間違いなく確率の高いセオリーは 「学校ならではの情報&その人が共感する情報」 よくあるのが、20代~30代は音楽と収入を増やす内容に興味があるからと言って、そのまま最新の音楽情報やファイナンス情報をウェブから引っ張ってきて流してしまうケース。残念ながら、まず読まれません。 なぜか? スマートフォンで情報が簡単に入手できる時代ですから、自分の好きな情報は専門サイトから入手しますし、学校からの情報である必要がないからです。 特に蓄財情報は危ない内容のものも含め世の中に散乱しているのが現状ですので、良かれと思って流した内容が間違っていると信用を落としかねません。